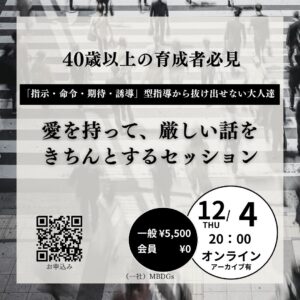SDGs後退の時代に感じていることと、「内側からの持続性」という視点
今、SDGsやESGをめぐる動きが変わりつつあります。その流れを見ながら、「では何が本質として残るのだろう」と考えていました。
Contents
SDGsをめぐる潮流の変化
脱SDGsの動きは、制度そのものを否定しているというよりも、「宣言と実行のギャップ」をどう埋めるかという課題が顕在化してきたように感じます。
企業の現場では、SDGsのポスターを掲げる取り組みが飽和し、スローガンより、現場の行動や価値創出が問われる段階に入っているようです。
外側の仕組みだけでは人は動き続けられないと感じます
SDGsの理念そのものは普遍的です。ただ、世界が直面しているのは「仕組みの限界」ではなく、“人の内側の限界”なのかもしれないとも思います。
どれだけ制度が整っていても、そこに向かう主体性や倫理観、内発的な理由が弱ければ、行動は続きません。企業の現場で聞こえてくる「再スキル教育がうまく機能しない」という声の背景にも、“内的動機の不在”や“価値の根っこの揺らぎ”があると感じることが多いです。
外側の目標だけでは、持続性は生まれにくい。SDGsの後退の動きは、その事実をよりはっきり示しているように思います。
SDGsの「次」を探し始めている企業や教育現場があります
最近、多くの現場で耳にするのは、「SDGsも大切だけれど、人の内側の部分に課題がある」という声です。
企業では人的資本投資やウェルビーイングへの関心が高まり、教育の現場では、主体性や自己信頼の弱さが問題視されています。
制度や枠組みよりも、個人がどのように選び、どのように動き、どのように関わろうとするのか。その“内側の持続性”が問われる場面が増えているのを感じます。
SDGsの後退は、その重要性を静かに可視化しているようにも見えます。
MBDGsという視点が大切にしてきたもの
MBDGsでは、外側の目標よりも先に“存在の根っこにある感覚”を扱ってきました。
自分は何に価値を感じ、どのように社会とつながり、どんな行動を選んでいくのか。
その基盤が揺らいでいる状態では、SDGsのような大きな目標に向かう力が続かないことを、教育や組織現場で強く感じてきました。
SDGsの後退は、内側から始めるアプローチの必要性を逆説的に浮かびあがらせているように思います。外側の目標が揺らぐほど、内側の基盤が重要になるという構造があります。
「内側からの持続性」という新しい問い
SDGsやESGが揺れるなかで、改めて問い直されているのは、“人はどこから持続可能性をつくるのか”というテーマだと感じています。
行動の源泉を、外側の制度や評価ではなく、自分の存在の中心に置くこと。
そこから生まれる持続性は、環境でも教育でも組織でも、静かに求められ始めています。
揺らぎの中で見えてくるもの
SDGsやESGの後退は、必ずしも悲観的な変化ではないように思います。むしろ、“内側なき持続性”がうまく機能してこなかった事実を示しているのかもしれません。
外側の仕組みが揺れるとき、内側の基盤がより鮮明に求められます。
いま起きている変化は、人の内面にある持続可能性へと視線を戻す、ひとつの契機に見えています。